Newsニュース
-1024x501.jpg)
Nakanoshima Qrossは、医療機関と企業、スタートアップ(SU)、支援機関等が「未来医療イノベーションの推進」という目的のもと、一つ屋根の下に集積する他に類を見ない施設です。この拠点において、具体的な共創プロジェクトを次々と生み出し、国内外へ発信していき、先進的な「未来医療イノベーション」に特化したスタートアップ育成エコシステムを構築しながら、日本発のユニークな産業・技術を基盤に世界へ発信するモデルケースを目指します。
「未来医療」とは、医療に対するニーズの移り変わりや科学技術の革新等、医療を取り巻く環境変化に常に即応しながら、その次の時代に実現すべき新たな医療と位置付けています。Nakanoshima Qrossでは【Nakanoshima Qross Future Forum】と題し、「未来医療」とは何か、その次の時代に実現すべき新たな医療とは何かについて、Nakanoshima Qrossエキスパートサポーターや産官学医の多様なステークホルダーとの対話を通じて、イノベーションを誘発し未来医療の産業化を加速させていくためのフォーラムを開催してまいります。
第1回目は手術支援ロボットをテーマに開催します。Nakanoshima Qrossエキスパートサポーターとの交流も含めて現地開催としたく、奮ってご参加ください。
【開催概要】
開催日時:2025年1月20日(月) 13:00〜16:00(ネットワーキング含む)(受付12:30~)
開催場所:未来医療国際拠点 Nakanoshima Qross 2階(Qrossover Lounge夢)
〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島4丁目3−51(アクセスマップ)
主催:一般財団法人未来医療推進機構
共催:大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻 未来医療学寄附講座
協力:MIRACLE SCIENCE INNOVTION株式会社
定員:80名(事前申し込み必要)
開催形態:現地開催のみ
参加費:無料
お申込みはこちらから(Peatixのサイトへジャンプします。)
【プログラム】
※予告なく変更する場合がありますがご了承のほどお願い申し上げます。
※また、プログラム内容については当サイトで随時アップデートをしてまいります。
12:30〜 受付開始
13:00〜(5分) オープニング
大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻 未来医療学寄附講座 寄附講座准教授/
一般財団法人 未来医療推進機構 エキスパートサポーター/
ジャパンバイオデザインプログラムディレクター
八木 雅和
13:05~13:25(20分) 特別講演1. 「Nakanoshima Qrossが目指す未来医療の姿」
一般財団法人 未来医療推進機構 理事長/
社会医療法人大阪国際メディカル&サイエンスセンター理事長・大阪けいさつ病院 院長/
大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻 特任教授
澤 芳樹
13:25~13:45 (20分) 企業セッション(仮)
*手術支援ロボット企業 事例紹介候補(5分x 4社程度 調整中)
13:45~14:25(40分) 特別講演2. 「ロボティクスサージェリーの最先端」
社会医療法人 大阪国際メディカル&サイエンスセンター 特別顧問/
一般財団法人 未来医療推進機構 エキスパートサポーター
竹政 伊知朗
14:25〜14:35(10分) 休憩
14:35〜15:25(50分) パネルディスカッション
ファシリテーター 八木雅和
パネリスト
スタンフォード大学医学部主任研究員/
Med Venture Partners,Inc取締役チーフメディカルオフィサー/
一般財団法人 未来医療推進機構 エキスパートサポーター
池野文昭
Link & Innovation代表取締役/
東北大学 スマート・エイジング学際重点研究センター 社会起業推進分野 特任教授/
一般財団法人 未来医療推進機構 エキスパートサポーター
山本晋也
TBD(スタートアップ企業)
15:25〜15:30(5分) 閉会挨拶
15:30〜16:00(30分) ネットワーキング
【登壇者ご紹介】

竹政 伊知朗
社会医療法人大阪国際メディカル&サイエンスセンター 特別顧問/
一般財団法人未来医療推進機構 エキスパートサポーター
大阪大学大学院医学系研究科を修了後、同大学で助教、診療局長、講師を経て、2015年に札幌医科大学消化器・総合、乳腺・内分泌外科学講座教授に就任。大腸がん治療の世界的エキスパートとして、国内外から多くの医師が手術見学に訪れる。大腸がん手術においては、新型ロボットのほとんどで日本初となる執刀を手掛けたほか、全国でも珍しいロボット手術専用手術室の整備にも取り組んだ。さらに、様々なタイプのロボット支援手術の普及に貢献し、札幌医科大学は手術支援ロボットの保有台数で全国トップとなり、大腸がん手術施行例でも全国有数の施設となった。また、多数の臨床試験で主任研究者(PI)を務めるともに、国内外39の学会で役職を歴任。日本内視鏡外科学会ロボット支援手術検討委員会では委員長を務め、導入指針の策定や若手医師の教育を通じ、安全なロボット支援手術の推進に寄与している。2024年9月より社会医療法人大阪国際メディカル&サイエンスセンター特別顧問、同12月より一般財団法人未来医療推進機構エキスパートサポーターに就任。
山本 晋也
東北大学 スマート・エイジング学際重点研究センター 社会起業推進分野 特任教授
Link & Innovation代表取締役
一般財団法人未来医療推進機構 エキスパートサポーター
連続起業家、社会起業家、経営者、投資家、Startup Mentor、社会物理学者。国内外のスタートアップを複数経営する傍ら、各大学で特任・招聘・客員教授等を兼任。Innovation Management、技術経営、政策科学、認知科学、digital health に関する学術・臨床研究、大学発スタートアップ・エコシステムの創出、産学連携推進、Global MBA等の教育活動に従事。中央政府各省庁の政策検討委員会委員、特別研究員等も歴任している。専門は、化学 (BSc)、分子生物学 (MSc)、技術・革新的経営 (PhD)。共創イノベーションのためのWeb 3.0/ DAOによる社会実験コミュニティ「DICT – Design, Innovation, Co-Creation, Technology」の創設者・代表でもある。
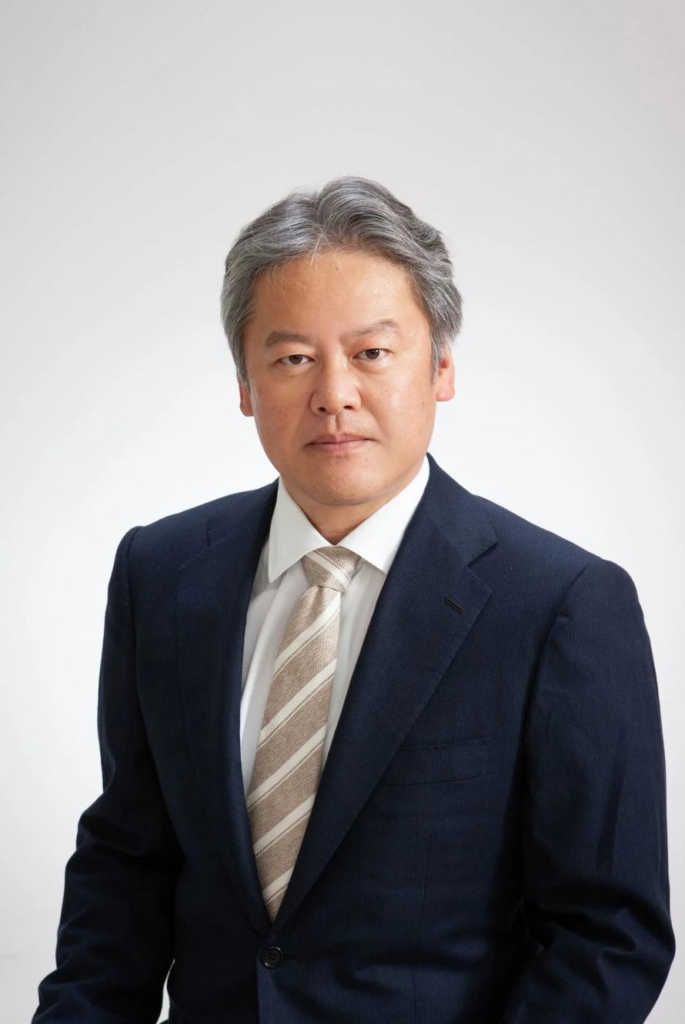
池野 文昭
Stanford Biodesign, Stanford University Program Director (U.S) Japan Biodesign,
MedVenture Partners取締役
一般財団法人未来医療推進機構 エキスパートサポーター
浜松市出身。医師。自治医科大学卒業後、9年間、僻地医療を含む地域医療に携わり、日本の医療現場の課題、超高齢化地域での医療を体感する。2001年から スタンフォード大学循環器科での研究を開始し、以後、14年間、200社を超える米国医療機器ベンチャーの研究開発、動物実験、臨床試験等に関与する。また、Fox Hollow Technologies, Atheromed, KAI Pharmaceutical, CV Ingenuity等、創業時から関与し、成功したベンチャーも多数ある。ベンチャーのみならず、医療機器大手も含む、同分野での豊富なアドバイザー経験を有し、日米の医療事情に精通している。 また、医療機器における日米規制当局のプロジェクトにも参画し、国境を超えた医療機器エコシステムの確立に尽力している。
スタンフォード大学では、研究と平行し、14年から、Stanford Biodesign Advisory Facultyとして、医療機器分野の起業家養成講座で教鞭をとっており、日本版Biodesignの設立にも深く関与。日本にもシリコンバレー型の医療機器エコシステムを確立すべく、精力的に活動している。

八木 雅和
大阪大学大学院医学系研究科未来医療学寄附講座 寄附講座准教授/
ジャパンバイオデザイン プログラムダイレクター/
一般財団法人未来医療推進機構 エキスパートサポーター
2003年に東京大学大学院 工学系研究科 電子工学科にて博士課程を修了後、大阪大学大学院歯学研究科助手、歯学部附属病院講師を経て、2008年に臨床医工学融合研究教育センター特任准教授に着任、生体の数理モデリング、および、専門家の知識を実装した意思決定支援システムに関する研究に携わる。2014年にスタンフォード・バイオデザイン グローバルファカルティ研修を修了後、ジャパンバイオデザイン立ち上げに参画し、2015年にプログラム・ダイレクターに就任。2017年には、ジャパンバイオデザイン フェローシッププログラムを開発・運営するサステイナブルな体制を構築するために、大阪大学大学院医学系研究科にてバイオデザイン学共同研究講座を立ち上げる。
