Newsニュース
2025年10月8日(水)、TKPガーデンシティPREMIUM横浜ランドマークタワー(横浜市)にて、「NakanoshimaQross Future Medicine Forum in YOKOHAMA」を開催しました。

本フォーラムは、厚生労働省「創薬クラスターキャンパス整備事業」に採択された「Nakanoshima Qross創薬・実用化促進プログラム等支援事業」の進捗を紹介し、国内外のスタートアップや投資家、製薬企業との新たな共創を促進することを目的に実施されたものです。
「未来医療の国際拠点」として大阪・中之島に拠点を構えるNakanoshima Qrossは、医療機関・企業・スタートアップ・支援機関が一体となり、創薬シーズの実用化から社会実装までを一気通貫で支援する仕組みを整備しています。
本フォーラムでは、政策的背景やNQの取り組みに加え、支援対象スタートアップによるピッチ、グローバルファーマやアクセラレーターによる最新の取組紹介、CDMO事業の発展に向けた議論など、多角的な視点から日本の創薬エコシステムの可能性を探りました。
冒頭の主催者開会挨拶冒頭では、澤 芳樹 理事長により日本の科学技術を社会実装へとつなぐ新たな挑戦として、「中之島クロス創薬クラスターキャンパス事業」のビジョンと戦略が示されました。今後は、CIC、Plug and Play やLINK-J等インキュベーター・アクセラレーターとの支援体制の拡充を通じて、グローバル水準のインキュベーションの推進と、起業家的人材の育成を強化していきます。さらに、CDMO事業の推進や国際連携の拡大を通じ、世界50カ国以上との協働を進めながら、まさに「サイエンスの価値に投資する場」としての「サイエンスカジノ」の比喩を交えながら、中之島から世界へ、と決意が述べられました。


次に安中 健 氏(厚生労働省 医政局医薬産業振興・医療情報企画課長)からは、日本の創薬力強化に向けた国の政策的背景と、創薬クラスターキャンパス事業の位置づけについて説明がありました。
まず、医薬品モダリティの多様化により、創薬は低分子化合物中心の時代から、バイオ医薬、細胞医療、遺伝子治療へと拡大し、研究開発は高度化・複雑化している現状が示されました。この変化の中で、アカデミアやベンチャーとの連携による水平分業が世界の潮流となっており、日本でもその体制強化が急務であると指摘されました。一方で、海外では進む革新的医薬品の創出に対し、日本では開発・導入が遅れる「ドラッグラグ」「ドラッグロス」問題が再燃しており、特にベンチャー発の医薬品で開発未着手が多い現状が報告されました。こうした課題に対応するため、政府は創薬を国家の基幹産業と位置づけたうえで、官民連携による実行体制を強化しています。その一環として「創薬クラスターキャンパス整備事業」を推進し、大阪・中之島をはじめ全国の拠点でスタートアップ支援とエコシステム構築を展開しています。また、革新的医薬品の継続的な実用化を支えるため、「実用化支援基金」を新設し、官民出資によりインキュベーション活動を後押しする仕組みが紹介されました。





次に「Nakanoshima Qrossにおける創薬クラスターキャンパス事業への期待」をテーマに澤 理事長、宮川 潤 理事長補佐のダブルモデレーターでパネルディスカッションを行いました。
本セッションでは、中之島クロスを核にした創薬クラスターの“実装フェーズ”をテーマに、グローバル展開、アクセラレーション、CDMO・臨床ネットワークまでを一気通貫でどう整えるかを議論しました。
まず、岩崎 誠司 氏(Plug and Play Japan Senior Manager, Health)からは、世界約60拠点のネットワークと投資/アクセラレーションを両輪に、国内外の病院・製薬・医療機器企業との協業を通じてデジタルヘルスのスケールを後押しするモデルを紹介。拠点間連携でイン/アウトバウンドを仕組み化し、中之島との共同でJPM Week(26年1月。「J.P.モルガン・ヘルスケア・カンファレンス」が開催されるウィークのこと))にあわせた実戦的な海外展開支援(BioTech Showcase の1on1マッチング、現地事業会社紹介、サイドイベント活用等)を実施する計画が共有されました。
次に加々美 綾乃 氏(CIC Institute Assistant Director)からは、オフィス提供に留まらず、大規模なイベント運営・コミュニティ形成・海外展開支援を組み合わせる“イノベーションキャンパス”運営モデルを提示。東京拠点の運営実績を基盤に、26年春に国内3拠点目として中之島でも開業し、ライフサイエンス特化の場づくりとプログラム運用を加速し、国内外ステークホルダーを継続的に呼び込む仕組みを整える方針が示されました。
石井 喜英 氏(Alloy Therapeutics 株式会社 代表取締役社長(Chief Executive Officer) )からは、ベンチャースタジオ型の創薬モデルを紹介。「頭金は最小に、広く支援して臨床入りを最大化」を基本思想とし、2年以内/数億円規模で候補到達を要件化する高速・低コストの進め方を強調。米欧の最先端技術と運営ノウハウを取り込み、中之島プロジェクトでも“二人三脚”の事業化伴走を適用する考えが示されました。
パネルディスカッションの課題と打ち手としては、①“死の谷”突破は情報戦(製造可能性、治験設計、PDマーカー、競合・採用理由、投与経路まで踏み込んだピッチ設計)、②株式設計とガバナンス(中長期の調達に耐える希薄化管理)、③海外拠点戦略(高コスト地域の代替案を含む物理拠点確保)を具体論で整理。さらに、中之島のCDMO を“公共性の高い受け皿”として機能させ、臨床試験ネットワークと海外KOL連携を結ぶことで、規制対応~PoC~導入までのボトルネックを段階的に解消する構想が共有されました。
最後に、支援は“選抜的に深く”という運用原則を確認。採択母集団は広く確保しつつ、海外展開支援など重厚な伴走は少数に集中することで成果の質とスピードを高める方針です。中之島クロスは、各アクセラレーターや伴走支援者の強みを束ね、グローバルパートナーとの早期関係構築→実装へ踏み出す次の一手を明確化しました。


次のパートでは「本事業の支援対象スタートアップご紹介(海外渡航プログラム)」として、まずは村尾 崇実 氏(一般財団法人未来医療推進機構 スタートアップ支援部マネージャー(経済産業省近畿経済産業局))より創薬スタートアップの海外展開を支援する派遣プログラムの方針説明を行いました。本支援プログラムは、資金調達・国際連携・臨床試験体制構築を目的に、米国などでの活動を後押しするもので、中之島クロスの医療機関・企業・アカデミアネットワークを活用して展開されます。説明後、支援対象のスタートアップ9社によるピッチを行いました。
(支援対象スタートアップ9社はこちらから:https://nq20251008.peatix.com/view)

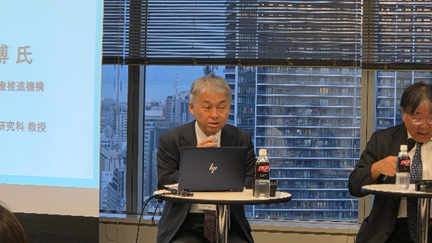



本セッションでは、再生医療等製品の産業化を加速する実装論を、大学・産業・行政の視点から多角的に議論しました。まず、臨床・技術が先行した再生医療の現場においては、標準化や指針整備を含む「設計力」=工程を考える力の強化が最優先課題であり、作る人材だけでなく工程設計人材の育成を中核に据える必要が確認されました。行政面では、創薬ベンチャー支援基金(総額3,500億円)やCDMO拠点整備の枠組みが紹介され、認定VCの出資を呼び水にパイプライン単位で支援を重ねる運用が共有されました。国内に製造の受け皿を持つことは経済安保の観点からも不可欠で、日本の強みであるiPS細胞を軸に受託産業としてのCDMOを外貨獲得産業へ育てる方向性が示されました。
大量製造については、従来の小スケール開発から多能性幹細胞を活かした量産への転換が鍵であり、需要拡大を見据えて「原薬となる細胞」を先行確保し、装置・システム面のブレークスルーを促す方針が共有されました。一方、産業化の勝負どころは“D(開発)”で、CDMOへの技術移管に約6か月を要する現状がボトルネック。小スケールで量産条件を再現するスケールダウン検証と、そのデータに基づく前向きシミュレーションの両輪で移管短縮とコスパ改善を図る必要性が示されました。特に分注・凍結工程での細胞損失は早期に教育・標準手順へ反映すべき重要論点として整理されました。
中之島クロスでは、CDMO、培養装置メーカー、技術者などの集積を活かし、「持ち込めば何とかする」発射台/滑走路として“究極のおせっかい”で伴走するエコシステム像を提示。中之島クロスで、26年設置予定のパイロットスケールプラントを中核に、共同開発の成果はメーカー側の実施権を確保しつつ、コンソーシアムでも自由活用できる運用で統合システム型のCDMO事業を推進します。さらに、スタートアップのインキュベーション/人材育成/CDMOを三本柱とする「KOC(究極おせっかいセンター)」構想を掲げ、教える側⇄学ぶ側の循環で“分かる人”を増やす仕組み化に踏み出します。
未解決事項として、基金残高・配分計画の透明化、2030年需要に向けた量産ロードマップの定量化、D機能の評価ツール/プレイブック整備、テックトランスファー標準化(責任分担・期日設定)が挙げられ、次フェーズのアクションとして数値とマイルストンに基づく実行計画の早期提示が求められました。
フォーラム終了後のネットワーキングでは、登壇者、参加者間で活発な意見交換が行われ、分野や立場を超えた交流が生まれました。
今回のフォーラムは、日本の創薬力と再生医療の産業化を推進する「中之島モデル」の可能性を具体的に示すとともに、国際的なネットワークと共創を通じて未来医療の社会実装を加速するための大きな一歩となりました。中之島から始まるこの動きが、世界とつながる創薬・医療イノベーションの新たな波を生み出していくことが期待されます。
